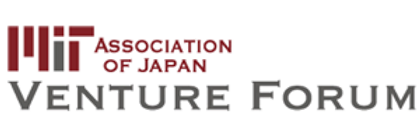今月は、コンテスト形式で2001~2020年のあいだ開催していたBPCC(ビジネスプランニングコンテスト&クリニック)第18回ファイナリスト、デジタルグリッド株式会社代表CEO、豊田祐介さんにお話を伺います。
デジタルグリッド株式会社は、2025 年 4月 22 日、東京証券取引所グロース市場に上場されました。
東証グロース市場上場までの道のり
- 大野
- このたびはデジタルグリッド社の東証グロース市場上場、誠におめでとうございます。
上場を果たされた今、率直にどのような想いをお持ちでしょうか?
- 豊田
- トランプ関税のこともあり、タイミングとしては株式市場が非常に不安定な時期ではあったので、直前まで本当に上場できるかできないか、するべきかするべきではないか…みたいな議論はすごくありました。
今は投資家の皆様の期待があって上場できているという状況ですので、まずはそこに対してほっとしている気持ちです。
投資家の皆様への感謝の気持ちはありつつ、やはり資本市場の波に晒されている状態ではあるので、いざ実際にその立場に立ってみると、今までにも増して身が引き締まる思いですね。
- 大野
- 上場直前と直後で、大きな違いは感じましたか?
- 豊田
- そうですね、やはり事業に対する説明責任みたいなところは、非常に大きいかなと思っています。
会社が相当辛かった時期もあって、そういったところから支えてくれる株主様、つまり阿吽の呼吸で僕らを見てきた投資家の方々や、パブリックインフォメーションしか持ってない中で僕らを信じて投資してくださる皆様への、説明の仕方となどは、「いや、そう言わなくても、これぐらいわかるでしょう」というような甘えみたいなものが、多分にあると思っています。
投資家の方々に対する説明をするところが一番苦労しているというか、勉強をしているところですね。
- 大野
- 「本当に上場したいの?」って思うくらい、上場というのは、する前もしたあとも大変なんですよね。
その大変さ含めあらゆることでご苦労されたかと思いますが、想定通りだったのでしょうか?
それとも、実際に上場しようとなって、「すごく大変!」と思いましたか?
- 豊田
- そうですね。
勤怠管理とか内部監査やJ-SOXなど当たり前ですけど初めて取り組むことや、今まで以上にしっかり取り組まなければならないことも数多くあり、いざやってみると、やはり本当に実務メンバーがだいぶ疲弊するぐらい大変でした。
上場したらしたで、また今度は投資家の皆さんからの厳しい質問にも晒されるみたいなところはあるので。
想像以上にやはり大変だったなというのが実感です。
では、なんで上場するのかというと、今、再生可能エネルギー業界っていうのは、蓄電池という新しい波が来ている中で、今一度大きく舵を切って踏襲していきたいみたいな思いがありました。
方向性とか、金額規模みたいなところも、未上場の時と比べると、また違う規模感になります。
未上場の状況ですとどうしても主要な株主の方々でも、株主間契約というのがあったりして、株主の方々との歩調を合わせながら、戦略みたいなところをずっとやっていたんですが、上場すると当然、特定株主との間の契約というのは、すべてアンワインドになり、基本的には特定株主に対する利益は全くできない。
フェアな状況になる中で、よりスピード感を持って、投資とか新しい事業領域にチャレンジできるのではないかなという思いもありました。
新しい事業をやりたくて、その中でスピード感も持ちたかった。
そういう点がところが、上場したかった一番大きな理由になるかもしれないです。
- 大野
- なるほど。
最近コーポレートガバナンスが大きく変わってきていて大変ではありますが、グロースはプライムやスタンダードほどは厳しくないので、伸び伸びとやっていかれたらいいですね。
ミッションは「エネルギーの民主化を実現する」
- 大野
- 貴社のミッションと、事業内容を分かりやすくご紹介いただけますでしょうか?
- 豊田
- 我々のミッションは「エネルギーの民主化を実現する」で、ビジョンは「エネルギー制約のない世界を次世代につなぐ」です。
資源、エネルギー制約から解放された世界を、次世代に繋ぐというようなことです。
特にここ10年〜15年、3.11で原発が一時的に止まってしまってからの日本は、電力の業界はかなりアップデートが進んでいると思っています。
今までは、沿岸部に大きな火力発電所や原子力発電所を用意していて、中央集権型で一気にそこで発電したものをディストリビューションするという、こんなビジネスモデルだったわけです。
しかし、この10年間でもっとディストリビューティングされた電源、すなわち太陽光だとか風力というのがいたるところにある。
つまり電力の流れが一方向だったものから、双方向にいろいろなところに、電圧の低いところにもあるしもちろん高いところにあるという、双方向に融通される世の中に、この10年、15年でアップデートされていると思っています。
それをより支えていくような社会インフラを作っていくことで、要はエネルギーを制約なく自由に使えるようなものが、最近増えてきている。
分散電源って再生可能エネルギーが主ですので、再生可能エネルギーは、もう読んで字のごとくで、使っても使っても、次から次へとなくならない、地球が存続する限りなくならないエネルギーで、かつ限界費用が実質ただみたいなもの。
こういったエネルギーを増やすためのインフラを提供しています。
具体的に言うと、そういう電源が欲しい人、売りたい人がマッチングできるような、電力の売買プラットフォームを運営しているという、こんな会社です。
- 大野
- お客様は誰になるのでしょう?
- 豊田
- お客様はBtoBがほとんどで、法人の方で、非常に多くの電気を使っているとか、そういう方々が主になります。
例えば製造業、工場とか…あと意外と需要があるのが、ホテルとか小売業さんでしょうか。かなり改善して利益を突き詰められている方で、ちょっとでも電気代を安くしたいような、多店舗展開されているホテル、病院、小売、製造業……そういったところが多いかなと思います。
- 大野
- なるほど、例えば私がホテルを経営しているとすると、電気をより安定的に安く供給してくれるところを探している……そういう場合にデジタルグリッドさんにコンタクトを取って電気を買うということなのでしょうか?
- 豊田
- おっしゃる通りです。
従来は電力会社から電気を買うのがほとんどでした。
電力会社との相見積もりを取るぐらいが今までの商流だったと思うのですが、それってすなわち電気を小売り価格でご購入されることに近いのですが、その小売会社さんがやる仕事をちょっとソフトウェアで自動化することで、1つ上流の卸しの世界から直接電気を引っ張ってくることを可能にするので、電気の価格が小売価格から卸価格になります。
我々がそういうプラットフォームとソフトウェアを提供して、その手数料が価格に追加されるのですが、従来、人の手でやっていることをソフトウェアに替えているので、我々の手数料の方がはるかに小さいです。
基本的には買い手にとっては電気が安く買えるし、売り手にとっては高く売れる。
- 大野
- つまり中抜きという感じでしょうか。
- 豊田
- 中抜きの部分をソフトウェアに替えているという感じですね。
あとは電力の売買をやっている方々の仕事を、AIとかシステムに一部変えてしまう。
- 大野
- そうすると、御社はどこかから電力を買わなきゃいけないわけですよね。
買う方はどういう仕組みになっているんですか?
- 豊田
- 我々自身が何か買うというよりは、売り手をたくさん連れてくるという形だと思います。
再エネ(再生可能エネルギー)の人たちはもう今は補助金がほとんどつかないので、買ってくれる人を常に探している状態です。
最近の日経新聞などで再生可能エネルギー事業者が相次いで倒産というような記事を見たのですが、ペインは確実にあります。
この10年間、固定価格買取制度を通じて電力を作ったら政府が買い取ってくれていたのですが、2022年から順次そういう制度がなくなっていっています。
売り主の方々は自分で作った電源を誰かに売らなくちゃいけない世の中に変わっていって、かなり苦しんでいらっしゃるので、喜んでこのプラットフォームにご参加いただけるのかなと思っています。

- 大野
- ということは、その売りたい人への営業っていうのはする必要がないわけですね?
買いたい人に対してだけ営業すればいいくらいに、売りたい人がたくさんいるということですか?
- 豊田
- そうですね、再エネの人たちにペインがあるので、そういう形です。
ただ、太陽光や風力などの再エネだけだったら、24時間電気を賄えないので、再エネだけでは成立しないのも、またこれは面白いところでして。
火力も非常に重要なので火力の人たちにも参加してもらい、雨が降っている日や、風が吹かない日などに、バックアップで入ってもらうことで、火力と再エネがお互いが支え合っているようなプラットフォームになっています。
電気使用量を予測して予約する、送る
- 大場
- 先ほど再生エネルギーを売りたい人と購入したい方をつなげるプラットフォームの提供っておっしゃっていたと思うんですが、例えば私が売りたい人だった時に、御社のこのプラットフォームを使うと、どんなサービスなんだろうっていうのが、ちょっとイメージがわかなかったので、そこを具体的に教えていただけますか?
- 豊田
- 僕らが提供できているサービスで、皆さんのペインを取り除けてるなと思うのは、電気を送るサービスのマッチングもするところです。
誰々さんと誰々さんでマッチングして交渉して、条件が合えば電気を送るというイメージができると思うのですが、そういえば電気ってどうやって送るんだっけって気になりませんか?
例えばメルカリとかでマッチングした後は、ヤマト運輸や佐川急便が高速道路を走って持ってきてくれるじゃないですか。
僕らはそのヤマト運輸とか佐川急便みたいなことも仕事としてやっていて、ここが多分一番イメージしづらいけど、大事であり難しい仕事だなと思っています。
というのも、運送会社の車と違って、電気って光の速度と同じで動いちゃう。
1秒間で地球7周半できるわけですよね。
つまり、電気をもう作っちゃったって言ったら、その瞬間に消費しないと、作ったけど使われないみたいなことが起きます。
結局何をするかというと、その発電所が次の24時間ないし、次の1時間でどれだけ電気を生み出すかというのを予測して、その予測下で電力量分の電線を予約しています。
既存の電線を使って電気を授受する場合は、電線の予約という行為が必要になります。
運送会社が荷物を運ぶ場合、時間指定は配達時間を午前指定にするとかで、東名高速道路を何時何分から何時何分まで移動しますから予約しますとか、絶対やらないじゃないですか。
これに近いことを、電力の世界ではやらなくちゃいけない。
それは一般の方同士だと、まずやりたくないし、そもそもできない仕事です。
その裏側はラストワンマイルのところで、且つ予測が間違っていると、ペナルティ的な精算をする必要があるんですよ。
「豊田くん、5時半から6時にかけて100という電気を送ってもらう約束なのに、なんか雨降っちゃって60しか発電できてないようだけど、どういうこと?40の分はペナルティ的な精算ね」簡単に言うとこんなルールになっているんです。
僕たちは、そのリスクを取り、皆さんがマッチしたら、その通りに電気を送り届けるように差配するみたいな仕事です。
- 大場
- その予想はAIを使っているんですか?
- 豊田
- そうですね、 今、拠点数で5000拠点ぐらいいるんですけど、5000人コンシェルジュがついていて、豊田裕介はこういう家でこういう電気の使い方をするという特徴を、それぞれの拠点ごとに学ばせたAIで予測をしています。
- 大場
- そのAIも御社の特徴だったりするんですか?
- 豊田
- そうですね、これも社内で作っていて。
生成AIのエンジンを作っているというよりは、AIにどういうデータを食べさせるのか、うまく使いこなして精度の高いアウトプットを出すような使い方をしています。
電力の世界はアップデートされる 再生可能エネルギーに舵を切る
- 大野
- 東京大学時代の研究から今のビジネスに至るまで、再生可能エネルギー分野に取り組み続けてこられた背景には、どのような問題意識や原体験があったのでしょうか?
- 豊田
- 問題意識というよりは、電力の世界がアップデートされるっていう、結構強烈な思いがありまして。
ちょうど僕が研究していたところの前後ぐらいで、2011年の3.11が起きて一時的に原発で止まってしまってその中で、再エネに舵を切ろうというような、政府(当時は民主党政権)の意思決定がある中で、電力の世界はアップデートされるだろうなと思いました。
そのアップデートされる世の中というのは、エネルギー自給率も上がり、限界費用も低くなっていくので、要は今までみたいに貿易で交渉して、サウジアラビア、オーストラリア、オマーンなどから石油石炭エネルギーを買う必要はなくなり、エネルギー的に自給自足できるし、且つそのエネルギー代も安いという世界が来ると思いました。
エネルギーを自由に使える世の中が来るんじゃないかなと思っていて、それが非常に面白いなと学生時代から思っていました。
ラーメンに喩えたら「全部の乗せ」、そこからシンプルな醤油ラーメンに…
ソフトウェアに絞る戦略
- 大野
- 製品・サービスを技術研究から事業に落とし込むまでに直面した最大の技術的な壁と、それを乗り越えたプロセスを教えてください。
- 豊田
- 電力なので、結構実証は大事だったのですが、環境省から実証のプロジェクトをもらえました。
うちの会社の設立が2017年で、その実証のテーマをもとにこれを商業化しようというコンセプトを掲げて、MIT-VFJのビジネスプランコンテストに大学の教授と一緒に参加したのが翌年2018年です。
メンターは藤井さんで、技術やアカデミックのバックグラウンドの方で、すごく丁寧に密に見ていただきました。
藤井さんは、常々ビジネスに落とし込むために、もっとマーケットのことを考えろ、売り方を考えろと、口を酸っぱくしてご指導いただいたことは今でもよく覚えています。
当時、我々はそういうプラットフォーム、つまりソフトウェアの提供と、セットでハードウェアも提供しようと、実際に電気を制御するところまでやっちゃおうという、ベンチャーからすると、巨額な投資が必要になるようなビジネスプランでした。
MIT-VFJへのビジネスプラン自体もそれで参加させていただいて、「よし、これで行こう」と動いていたのですが、2019年の6月にお金が底をついてしまって。
それまでは私は創業メンバーではありますが代表ではなく、当時は東大の阿部先生が代表をされていたんですよね。
先生ともたくさん議論をして、ハードとソフトといろいろある中で、ソフトウェアのビジネスモデルにフォーカスをしようとなりました。
あれもこれもどれもやるとベンチャーだとなかなか厳しいので、リーンスタートアップじゃないですけど本当に贅肉をすべて落として一番コアな部分、つまりソフトウェアの部分をやった方がいいんじゃないかというのを、先生ともお話をさせていただきました。
2019年の7月ぐらいから僕が代表をしているというのはそんな状況でした。
当時やろうとしてたビジネスモデルはラーメンにするともう全部乗せみたいなものでしたが、シンプルに醤油ラーメンだけでやろうと。
なんだったら、ちょっとメンマが乗っかるぐらいな感じで。
やりやりたいことはたくさんあるけれど、全部はできないから捨てなくちゃいけないという意思決定をしたというところが難しかったですし、そこが一番のきっかけだったかなというところがありますね。
- 大野
- それが今の成功につながったっていうところですね。ソフトウェアウェアに絞った。
- 豊田
- そうですね。
アカデミックのベンチャーにあるあるかもしれませんけど、どうしてもプロダクトを愛してしまうが故に、プロダクトアウト寄りの思考に、今でも僕はなってしまうんですが、やはりマーケットがないとビジネスが成立しないので、出資してくれている株主が最初の初期ユーザーになって、実際に結構な金額を払ってくれたというのは、非常に大きなスタートになりました。
僕らがいいと思うプロダクトを押し付けるのではなくて、当然ビジネスなのでお客様が使ってくれるようにチューンナップするみたいなことに、もう1つ気づくというか。
まあ、当たり前のことなんですけどね。
6億円の資金集めをしたが、2019年に資金が底を突く危機が
- 大野
- まあね、なかなか切り替えができないんですよね。
プロダクトアウトからマーケットインにね、わかっていながら、なかなか難しいところですよね。
でもそれを乗り越えた、そして資金調達。
初期の資金調達において、どのようなご苦労がありましたか?
投資家との関係構築でのポイントもあればぜひ。
- 豊田
- そうですね。
最初は最初で大変だったんですけれど、東大発ベンチャーであったことや国からの実証もついていたためか、比較的応援してくださる株主様がいらしたのは確かです。
当時は議決権のない種類株で、ボードライトを持たずに出資をしてくださっている方が多くいらして、6億円弱ぐらいになりました。
シードマネーに近いのに億単位のお金をいただきました。
さきほどお話ししましたが、やはり一番大変だったファイナンスは、ハード、ソフト両方に投資した結果2019年にお金がなくなった時でした。
プロダクトがローンチできていればいいのですが、プロダクトもどっちもローンチできていないけれど、お金はない……みたい中で、当時株主様がもうすでに40社ぐらいいらっしゃって。
株主様からは「一体何をやってたんだ、信じて投資したのに、もう何億のお金を溶かしているのか!」みたいな厳しいお言葉をいただいたんですが、当時追加で4、5億円のお金が集まらなければ、もうソフトウェアだけに絞ったとしても、プロダクトをローンチできない、というような状態でした。
しかし、追加で出資してくれる方、もう本当に1人もいなくて。
既存の株主様の中には、もうなんか泥船だというふうに思ってらっしゃった方もいたかもしれません。
資金が底を尽き、追加で新しい株主様を探さなくてはいけないというタイミングで、社長が僕に替わりました。
僕が最初にやったことは、それこそ全従業員を整理解雇することや、家賃の支払いをちょっと待ってもらうとか、税金とかもそうなんですけどね、そういういう支払いができない中で、いろいろな人に迷惑をかけてきて3カ月間ぐらい経ってしまったんですけど。
この必要な4、5億円というお金を集めるというのが一番大変でした。
ものはできていなくて、ただ、想いだけがあって。
一応初期ユーザーで使ってくれそうな人たちはいたけど、時に契約をしてコミットしてくれているわけでもない。でもなんか世の中のためにいいと信じていますみたいなピッチで。
且つ、株主様も40社以上いる中で、その株主も「大丈夫なのか?」とちょっと荒れているムードの中で、VCさんなんかはもう一社も入れなかったんです。
日本にあるほとんどのVCさんにお邪魔して、資金状況もご説明して資金調達を試みたんですけど「いや、ちょっとそんなに株主様がいて、しかも荒れてるんでしょう?」 と。
最後の1〜2週間ぐらいまでどうなるかわからない中で、本当にギリギリのところで首の皮1枚でファイナンスが繋がったみたいなことがありました。
最後まで諦めずになんとかこう歯を食いしばってやったというのが、今でも思い出深いストーリーかもしれないです。
失業保険も給料もいらない 12人のメンバーが持ち場を守り抜く
- 大野
- いやあ、針のムシロですね。聞いているだけで胃が痛くなりますね。
よくまあ調達できましたね。
- 豊田
- これは全員野球とでも言いますか。
先ほど社員を整理解雇した話をしましたが、それは整理解雇すると早期に失業保険がもらえるからという理由もあったんです。
けれども、当時14人いたメンバーのうち12人は、失業保険はいらないから業務委託でもいいから残ると言ってくださいました。
業務委託しちゃうと失業保険がもらえません。
しかも、業務委託と言っても、資金調達がうまく行かなければ委託だってできない、働いてもらえないわけです。
それでも14分の12の方は、お給料が払われなかったとしても、働くと言ってくださって。
その皆さんが皆さんの持ち場を守った。
つまり実証をやっている人たちは実証がうまくいかないと、本プロダクトに行かないから、その実証を進め続けたし、広報メンバーはうちの会社は夢があると言って週刊ダイヤモンドに記事化していただいたし、経営メンバーに近い人はみんなで投資家を手分けして当たったりしました。
これは僕1人がすごかったとか、乗り切ったというのでは一切なくて、当時のメンバーみんなでなんとか繋いだというところです。
誰が出て行っていても結構厳しかったんじゃないかなということです。
- 大野
- よくそんな中で頑張りましたね。
もう本当に、大拍手です。
- 豊田
- そうですね、上場という意味で、先ほどいろいろなこと言いましたけど、もう1つ裏側にあるテーマとしては、そういう辛い時期を乗り越えた初期メンバーに対する、ちょっとした報いにはなるかなと。
当然家族とかも含めて、相当な危険と迷惑にさらしてしまったメンバーなので。
- 大野
- 上場直後の株価も良かったですね。
- 豊田
- でも本当に上場できるか分からなかったぐらいではあるので。
今まだワチャワチャしているところですが、ここから先はちょっと実力とコミュニケーションで伸ばしていくしかないというふうに思っています。
日本で初めてPtoP(Peer to Peer)での電力取引を認可される
- 大野
- いやー、なんかもうすごく嬉しいですね。
お話を聞いているだけでワクワクして。
人のことだと思ってワクワクとか言ってるけれど、そりゃあ大変でしたね。
よく乗り越えました。
- 豊田
- 資金調達が全部終わった後は、藤井さんにお祝い会みたいなのしていただいて。
- 大野
- そうですか、よかったよかった。
藤井さんはね、本当に素晴らしいメンターなんですよ。
藤井さんは、自治体というか行政というか、ガバメントに知識も経験もある人なので、すごく良かったですね。
ぴったりな感じです。
電力のフリーマーケットという革新的な仕組みを構築する中で、規制や業界構造とどのように向き合い、乗り越えてこられましたか?
- 豊田
- そうですね。
小売りをすっ飛ばして、最終ユーザーが卸のマーケットに直接行く、つまりマグロを買おうと思った時に、普通はスーパーとかで買いますが、豊洲市場に直接買いに行くというような話で、豊洲市場も電力もそうですけど、認められている仲卸業者みたいな登録してる人しか普通は入れないじゃないですか。
「自分はちゃんとマグロを市場でうまいこと切り分けるから何も心配しなくていい」とか「ちゃんとマグロを買うから」と、我々のソフトウェアを信じてルールとして認めてほしいということを、経済産業省の資源エネルギー庁が管轄になるんですが、その面々と協議をさせていただいていました。
End to Endが電力会社を介さずに行っていることを、我々は、電力のPtoP(Peer to Peer)取引と言っています。
ここは少し1つ大きなブレークスルーだったかもしれないです。
当時、ちょうど大学の同期で、資源エネルギー庁に行った人がいて、いろいろとつきあってくれて、新しい取り組みだしなんか面白いんじゃないかと、国としては思ってくれました。
こんな新しい取り組みなんて、別に既存勢力を脅かすほどのものでもないし、面白い取り組みだから、今の既存のルールの中で、どう整理したら認められるかというのを、国側がかなりフレキシブルに考えてくれました。
半年ぐらい一緒に協議したかな?
2019年の資金調達後の9月に、日本で初めてPtoPで取引してもいいですよという許可を出してもらった経緯があります。
これは、残念ながらそんな美しい話でもなくて、そんな小さなベンチャーだから、それに対して目くじらを立てる反対勢力なんていなくて、その中で新しい取り組みを認めていただいたということです。
そこから業績が伸びたというところで、漸く今は認知はされているとは思うんですけど。
- 大野
- 経済産業省って割と革新的な部分や考え方があるので、省庁の中ではなかなか進んでいるなというのは、私も体験したことがあって。
それは良いですよね。
- 豊田
- 自分たちの利益だけではなくて、国益とか、日本がちょっとアップデートする方法とか、「こうすると日本ってちょっとでも良くなるんじゃない?」という発想で話しかけると、非常にフレンドリーに聞いていただけるんだなと、その時に学びました。
棲み分けができているコンペティター
- 大野
- 同じような業務の会社というのは他にあるんでしょうか。
つまりコンペティターはいるんですか?
- 豊田
- こういうプラットフォームやってますみたいな売り方をしている人は、そんなに多くはなくて、あるとするとエネチェインさん。
彼らは電力のマーケットを作るデジタル化を進める、電力のデジタル化のアップデートをしている、仲間かなというふうに思っています。
このプラットフォームとして繋げているお客さんが彼らとは異なり、僕らはPtoPで、要は素人対素人を繋げるビジネスをしている。
エネチェインさんはプロとプロを繋げる。
例えばENEOSさんと東京ガスさん、東京電力さんと東北電力さんのように。
今までアナログな形で電気の取引をしているのを、そこにデジタルを使うというのが、エネチェンジさん。
プロの電力会社さんの価格.COMのような、電力比較サービスみたいなことをやっているので、三社三様ではあるんですが、電力の世界にデジタルとかソフトウェア力を持ってきて、アップデートするという思いは一緒なのかなと。
- 大野
- なるほどね。ちゃんと棲み分けされているわけですね。
MIT-VFJのビジネスプランコンテストの参加でマーケットを意識する
- 大野
- ところで、MIT-VFJのビジネスプランコンテストに応募されたのはどなたかに紹介されたのですか?
- 豊田
- 三菱商事の長野さんという方がいらっしゃるんですけど、長野さんがMITスローンの出身で。
長野さんが面白半分に「豊田くん、せっかくだから揉まれた方がいいよ」と言って、それで勧めていただいたというのがきっかけでした。
- 大野
- そうですか、長野さんはまだその時、メンターはやっていらっしゃらなかったのかしら?
- 豊田
- 今はメンターをなさっているんですか?
- 大野
- はい、メンタリングを担当してくださっていました。
海外にお住まいなので、オンラインで海外から。昨年はおやすみされましたけれど。
- 豊田
- ああ、そうなんだ! 当時はメンティーのデジタルグリッド社として長野さんも参加していました。
デジタルグリッド社に三菱商事も出資していたので。
三浦半島での合宿とか一緒に行きました。
- 大野
- まあ、そうでしたか! 当時、長野さんがチームの一員だったんですね! ビジネスプランコンテストに参加されて、どんな点が良かったですか?
- 豊田
- 結局それでうまくいったかはさておき、ビジネスに否が応でも繋げなきゃいけないじゃないですか。
マーケットがあって、売り上げがどうで、とか。
当時はプラットフォームの要件定義をしていたり、ソフトウェアをどうデベロップメントするかみたいなのを、僕はずっとやっていて。
僕は実は、新卒での就職先がゴールドマンサックスなので金融業界出身なんですよ。
だから事業計画とか数字を見ることのプロでそれを仕事にしていたのですが、いざベンチャーをやるとプロダクトが面白すぎて、事業計画の中のプロダクトのことばかり考えていました。
文字通りビジネスプランなので、ちゃんとエグジットとか、どういう売り上げでどうやってこのプロダクトがお客さんにかかるのかというのを、ある意味、ちょっと強制的に考えるきっかけになりました。
完璧プロダクトアウトの思考だったのが、マーケットのことも意識するようになった良いきっかけでした。
プレゼンとかも結構時間が短いから、ワンスライドワンメッセージでまとめなくちゃいけないじゃないですか。
そこは非常に頭の整理になりました。
我々は2017年の創業ではあるんですけど、オフィスを構えてやり始めたのは2018年の1月とか2月とかなので、合宿は2018年の8月でしたから、できて半年とかの会社なので、まあゆるい状態ではあったんですが、すごく良いきっかけになりました。
- 大野
- 豊田さんはその時は社長だったんでしたっけ?
- 豊田
- 社長じゃないです。企画課長ではあったんですが、3人ぐらいしかいない会社でしたから、要は何でも屋さんでした。
- 大野
- そうだ、19年に社長になったんでした。
- 豊田
- MIT-VFJのビジネスプランコンテストは、代表者しかピッチできなくて。
「お前、代表者じゃなくて、企画課長やろ」って言われたんですけど、「違います。僕はこの会社を代表する人間です」って言って、企画課長だけどプレゼンさせてもらっていました。(笑)
- 大野
- うーん、そうかそうか。
やはり最終的な責任を取る人じゃないと、合宿なんかでもどんどん違う方向に行ってしまったりするから、意思決定者じゃないと難しい面があるんですけどね。
よく頑張りましたね。
- 豊田
- この会社とのやりたいことって、学生時代の研究テーマでもあったし、当時の安部先生と一緒にやってたんです。
この思いはたがうことはないかなと思ったんで。
最終審査発表会での各務審査委員長による丁寧で的確なコメント
- 大野
- 他にMIT-VFJで印象的に残ったことはないですか?
最終審査発表会で賞を取られましたよね?
- 豊田
- 確か優秀賞をいただきました。
正会員特別賞もいただいて。MIT-VFJ正会員の皆さんに評判が良かったというものでしたね。
今でも各務さんは審査委員長をやられてるんですか?
- 大野
- はい、ずっと審査委員長をやってくださっています。ただ今は優劣をつけるコンテスト形式ではないので、コメンテーターのリーダー的役割を担っていただいています。
- 豊田
- 各務さんにご子息がいらして、ひょんなご縁で、今一緒にいろいろ学生に向けて活動してたりとかするので、結構狭い繋がりだなと思って。
- 大野
- そうですか、奥様も頑張っていらっしゃるみたいですし、起業一家みたいな感じですね。
- 豊田
- そうそう、息子さんもね、新しいビジネスが今年からが勝負なんだと言って、医療系のビジネスをやってますね。
- 大野
- 憶えていらっしゃると思うんですけれども、各務先生のコメントは本当に素晴らしいんです。
1人1人、1チーム1チームに、全て的確なコメントをくださるので、今年もまた楽しみにしています。
- 豊田
- そうですよね、できて間もないベンチャーですけど、1社1社すごく丁寧に見ていただいていました。
- 大野
- ありがたいことです。もうそれを聞くだけでも、最終発表会に行く価値がありますから。
これから起業を目指す方々、VMP25への参加を検討している人たちに向けてのメッセージ
- 大野
- これから起業を目指す方々、特にVMP25への参加を検討している人たちに向けて、ぜひメッセージをお願いします。
- 豊田
- 僕の場合、特殊かもしれないですけど、あまりVCさんからもお金いただいていなかったりとか。
そもそもだいぶシードだったということもあるので。
そういった意味だと、僕は初めて壁打ちをやって、ビジネスに対して自分がいいなと思ったことを、自分の主観とか、阿部先生とかとひたすら主観でやるだけではない、 第三者の意見が入ったのが多分このコンテストだと思います。
ちょっと繰り返しになってしまいますけど、やはり自分1人の主観で、プロダクトアウトになりがちだと思うんですよね、起業家の多くは。
こういうところで若干マーケットを見て、ちょっとひとつ冷静になって考えるとか。
まあ、場合によってはピボットするとかというきっかけにもなると思います。
シード期のビジネスが洗練されるなと思います。
メンターさんによるのかもしれませんが、少なくとも藤井さんはだいぶ遅くまで…深夜3時まで一緒にやっていました。
夕方8時ぐらいから10時ぐらいか、6時ぐらいから10時ぐらいまで3時間ぐらい続けて、平日とかもやってくださるぐらい、ちょっと普通のメンタリングのサービスを知らないですが、普通じゃないぐらいやってくださって。
すごくメンターが真剣なのが、このプログラムのいいところなんじゃないかなと思いますし、シード期の方には必ず血となり肉となる、糧になるようなプログラムだと思います。
- 大野
- 真剣すぎて喧嘩寸前?みたいになることも(笑)
- 豊田
- いやいや、本当に(笑) 喧嘩って言ったら喧嘩です、ほとんど喧嘩ですよ。
まあまあこうだからマーケットとかじゃなく…事業はこうで…いや豊田さん、マーケットをもっと見て…いやー…みたいなのはやりましたよ。
- 大野
- それを乗り越えられたわけで、素晴らしいです。
喧嘩じゃないんですけれど、へこたれて、さじ投げちゃう人もいたかなあ…大変です(笑) 愛あればこそ、ですよ(笑)
エネルギー制約のない世界を次世代につなぎたい
湯水のように使える再エネと、その調整力で作る未来の世界
- 大野
- 今後の展望として、日本のエネルギー市場、あるいはグローバル市場に向けて、どのようなビジョンを描いていらっしゃいますか?
- 豊田
- 本当に深いところでいくと、エネルギーの争奪で戦争なんて起きて欲しくないし、次の百年でそんなことが起こらないようにしたいという思いがあります。
それは夢物語ではなくて、どこの国にもその地の恵みみたいなのがあるので、太陽光だったり、風力だったり、地熱だったりというのはあるし、それを本当に有効活用すれば、エネルギー自給率っていうのは、本当は高い。
100%に近いところまで上がるんじゃないかなと、僕自身は思っていて、日本はそれは可能なんじゃないかなと思っています。
なので、僕らの子供とか、少なくとも孫の世代には、エネルギーという古臭いところで争うのではなく、それを湯水のように使って、どんどんイノベーションが起きるように。
違うことで、国と国がきちんと正しい競争するというようなものを作り上げたいと思っています。
だいぶ先のビジョンですが、その中でこの再エネが増えてきていること自体がすごくいいことだなと思っています。
ノルウェー、デンマークとか国によっては8割9割はもう水力で賄ったりする国がありますし、欧州とかだと3割4割5割とかというところが増えてきている。
日本だと今ようやく2割ちょっとで、先ほどの夢物語に近づけるためには、必要なのは調整力みたいなのです。
つまり再エネって結構1人前じゃないんですよね。
太陽光は雨が降っちゃうと発電しないし、風も止むと発電しないというので、1人前じゃない。
それを調整してくれるバッテリーの蓄電池なども非常に大事になってくると思っていますし、足元ではそういう再エネエネルギー自給率を高める行為に加えて、調整力…誰か面倒を見るような人たちというのは、非常に大事になってきています。
そこについては会社としてもコミットしたいなと思っています。
国によって進捗状況はまちまちですけど、いい国のいいものを勉強して、それをグローバルに伝えていけばいいかなと思います。
今はイギリスとオーストラリアは結構進んでいるので、去年はオーストラリアに行って勉強してきました。
来月もイギリスに行ってきます。
少し進んだ先輩方の制度と今の日本の制度を照らして、日本に対する提案をしてもいいし、逆に日本にあるもので向こうにないものもあるので、そこはそういうものをお互い伝えて切磋琢磨してくればいいのかなと思っています。
エネルギー問題の解決は、日本だけでやらずに、グローバルにやっていなくちゃいけないと思っています。
- 大野
- 御社ももちろん協力してインバルブしてやっていくとして、リーダーシップをとってやっていく人は誰なんでしょう?
その「調整」について。
- 豊田
- 蓄電池ですか。
日本国内とかだと、大手電力会社がずっとリーダーだったんですね、電力に関しては。
今でももちろんリーダーなんですけれども、大手電力会社さんはそういう小さな分散電源を作るよりも石炭や火力、原子力の発電など。これは万人に作れるものではない。
非常に限られた人しか作れないものを作るのがすごく得意なんですが、分散電源はちょっと違って、フットワーク軽く少し小さな電源をテンポよく作るところではあるので、そういうものづくりのリーダーは、この10年間でそういう分散電源を作ってきた人たちかなと思っています。
要は今までは上流から下流までリーダーは電力会社だったところから、まずものの作り手は大手ではなくなってくるし、それをディストリビュートするのも僕らみたいな新電力が入ってきています。
ここは一社で引っ張っていくっていうよりは、新しい人たちでやっていくみたいなことで、僕らも業界団体など作ったりしてやってるんですが、そういう新しいプレーヤーが業界団体を作って、それで国だったり政府に提言していくみたいなポーズかもしれない。
- 大野
- びっくりするような会社が参画してきたりする可能性だってありますもんね。
- 豊田
- ああ、それはあり得ると思います。
- 大野
- とてもエキサイティングなインタビューとなりました。
お忙しい中をありがとうございました。
ますますのご活躍、ご発展を祈っております。
豊田 祐介 氏 プロフィール
2012年に東京大学大学院工学系研究科を修了後、ゴールドマンサックス証券に入社。為替・クレジット関連の金融商品組成・販売、メガソーラーの開発・投資業務を担当。2016年よりインテグラルにてPE投資業務を行い、2018年2月にデジタルグリッド創業に参画。2019年7月2日に代表取締役社長に就任。

聞き手 大野一美
MIT-VFJ理事
▶プロフィールはこちら
聞き手 大場さおり
NTTドコモに新卒入社後、コーポレートブランディング、コーボレートコミュニケーションの分野に長らく従事。
展示会等のイベント、広告制作、ドコモ未来フィールドの立ち上げ等対外発信戦略の立案と実行を担う。
2025年より兼業でMIT-VFJ広報を担当。
「未来を担う人々が日本、さらにグローバルへ羽ばたいていけるように」「日本のビジネスや伝統文化などの良さを海外・国内と広く広める」を自らのmissionととらえ、ファイナリストやMIT-VFJの情報発信を担う。